女性患者の紹介が生まれる院が実践している7つのポイントをご紹介
接骨院を経営していて、女性患者数を増やしたいと思ったとき、あなたは何に取り組みますか?色々な施策がありますが、紹介数を増やすことは女性患者数を増やす最も有効な取り組みのひとつと言えます。
絶えず患者の紹介があり、女性の新患を獲得できる院と、なかなか紹介数が増えない院には、どんな違いがあるのでしょうか。紹介の生まれる院が実践している7つのポイントをご紹介します。
女性患者へ「紹介してください」と伝える

女性患者さまの紹介を増やしたいのなら、まずは女性患者さまに「紹介してください」と率直に言葉で伝えることが大切です。女性患者さまの痛みを取ることができたら…、女性患者さまの満足度を上げられたら…、確かに紹介をしてもらううえで大切な点かもしれませんが、これだけでは劇的な紹介数の増加は見込めないでしょう。
女性患者さまは、紹介をしたい理由がないのではなく、紹介をするという発想がない場合の方が多いのです。「紹介してください」と伝える。簡単なことですが、実践している院としていない院では明らかに紹介数に差がついてきます。
女性患者さまへ伝えるタイミングを決める

いつ女性患者さまに紹介をお願いするのかをあらかじめ、院のスタッフと共有しておきましょう。
その際、工夫するとすれば、具体的な相手をイメージできる声かけをすることです。「どなたか紹介してくださいね」とお伝えしても、女性患者さまはその「誰か」がなかなか思いつかないのです。「お友達でも同じような悩みを持っている方、多いですか?もしいらっしゃったら、ぜひご紹介してくださいね。」など、自然な会話の流れの中で、紹介したい人をイメージさせましょう。そうすることで、売り込みが強くなりすぎず、自然と女性患者さまに受け入れてもらいやすくなります。
【おすすめのお声がけのタイミング】
- 施術中
- 施術が終わったとき
- お会計が終わったとき
- 3回目の来院時
女性患者さまへ繰り返し紹介を依頼する

女性患者さまに「紹介してください」と伝えることは重要ですが、たった一度伝えただけでは、紹介数は増加しないと言えるでしょう。なぜなら、ほとんどの患者さまは紹介をお願いされたことは、家に帰る頃にはすっかり忘れてしまうからです。特に家事や育児に忙しい女性はなおさらです。何度も何度も繰り返し紹介をお願いすることで、「周りに身体がつらそうな人がいたら、この接骨院に紹介する」という意識を女性患者さまに刷り込むことが大切です。
また、「伝える方法」を変えてみるのも、テクニックのひとつです。来院の際、口頭で伝えるのはもちろん大切ですが、紹介カードなどの紹介ツールや、院から配信するメール、SNSなどにも紹介のお願いを定期的に盛り込みましょう。口頭で伝えるのは気が引ける、なかなか徹底できないという場合は、院内の女性患者さまの目につきやすい場所に紹介を依頼するポスターなどの掲示物を貼っている院も多いです。
紹介ツールやSNSでの情報発信には、口頭でのお願いにはないメリットがあります。それは、院にいない時間に院のことを思い出してもらえるということ。家に着く頃には紹介のお願いをされたことを忘れている、と先にお伝えしましたが、家に着いた後にカバンから紹介カードが出てきたら…、家族や友達と過ごしている間に院からメッセージが届いたら…、「そういえば、紹介をお願いされていたな」と院のことを思い出してもらう機会を増やせるのです。その場に一緒にいる方に、院の話をしてくれる可能性も高まるでしょう。
院での会話をあまり覚えていない患者さまも多いので、繰り返し伝えても問題はありません。しかし、もしもしつこいと嫌がられたら、それは売り込みが強すぎるのかもしれません。あくまでさりげなく、方法を変えながら、繰り返し「紹介してください」を伝えるようにしましょう。
紹介力がある女性患者さまを見極める
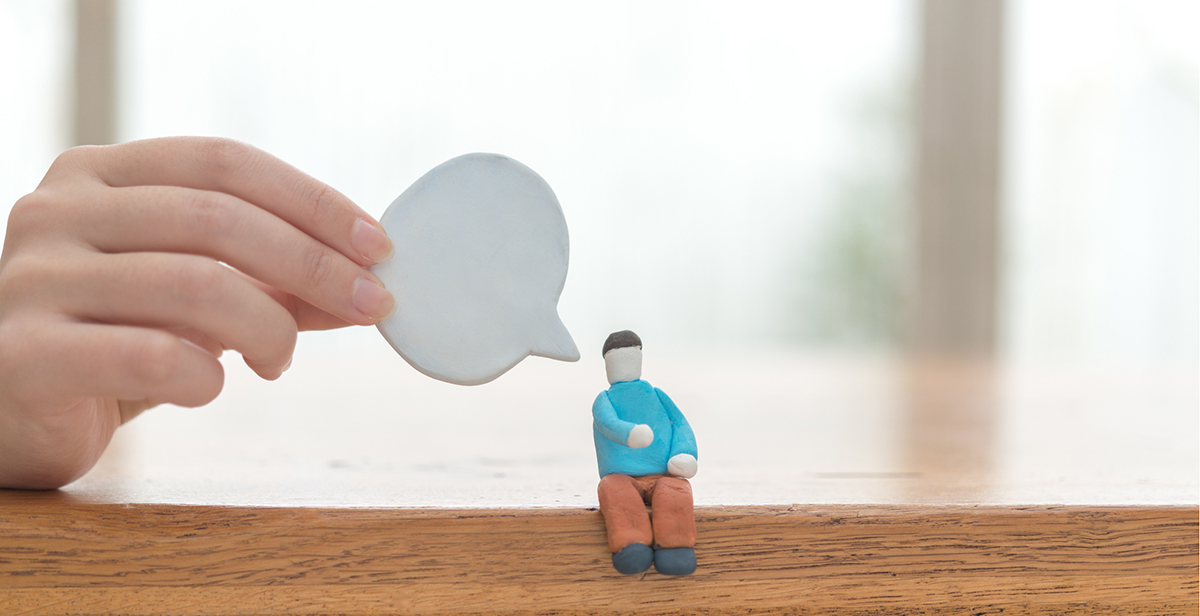
実は、紹介力のある女性患者さまであれば、ひとりで10人以上の方を紹介してくれるということは珍しくありません。
誰が誰を紹介したかはきちんと記録していますか?よく紹介してくれる女性患者さまがいる場合は、その方たちの共通点を探してみましょう。年齢は?趣味は?家族構成は?もしかしたら同じ施術を受けているかもしれませんね。その方たちの共通点が分かれば、それに当てはまる他の女性患者さまにも紹介をお願いすることで、女性患者さまの紹介数がさらに増える見込みがあります。紹介を生む“キーパーソン”を見つけましょう。
紹介してくれた女性患者さまに状況と感謝を伝える

紹介を受けたら、紹介してくれた女性患者さまに、状況と感謝の気持ちを伝えるようにしましょう。家族やお友達、大切な方の健康をまかせていただいたのですから、紹介してもらって終わりは厳禁です。「●●さま、身体の調子が良くなったと喜んでくださいましたよ!ご紹介ありがとうございます。」など、必ず紹介をしてくれた方に後日お話しましょう。
先に記述したように、1人でも紹介をしてくれる方は、さらに何人もの女性患者さまを紹介してくれる可能性が大きいです。紹介した後、院のスタッフから無反応では次の紹介のチャンスを潰してしまうことになりかねません。さらなる女性患者さまの紹介を生むためには、紹介後のフォローまで気を配ることを忘れないでください。
報酬と引き換えに依頼しない

紹介を促したいとき、多くの接骨院がやってしまいがちな注意点があります。それは、目に見える報酬制度にしてしまうことです。「紹介してくれたら〇〇円引き」「紹介してくれたら〇〇をプレゼント」などは避けてください。なぜなら、よく紹介をしてくれる患者さまは、紹介によって自分のお友達が喜んでくれること、院のスタッフに感謝されることを嬉しいと感じる人が多いからです。
ただし、目に見える報酬ではなくても、紹介者に感謝の気持ちとしてちょっとしたサービスを提供するのは効果的です。このときのコツは、値引きなどではなく「体験」を提供することです。フットマッサージや美容鍼など、「人に話したくなるような価値ある体験」の方が値引きより嬉しいと感じやすく、「もっとたくさんの人をこの院に紹介したい!」いう気持ちになってもらいやすいです。
これは「返報性の法則」といって、相手から受けた好意に対して「お返し」をしたいと感じる心理のことで、ビジネスの場でもよく利用されています。紹介をしてくれた人へ、目に見える報酬ではなくサービスの形で感謝の気持ちを提供することで、次回以降の紹介の動機づけになります。
自院の情報を発信する

以上が女性患者さまの紹介を生むための基本ポイントですが、すべて実践したら、ぜひプラスで取り組んでほしいことがあります。それは、常に最新の情報を発信し続けることです。
例えば、既存の患者さまがどなたかに口頭であなたの院を紹介してくれたとします。ここで、その紹介を受けた方の次の行動を考えてみましょう。すぐに院に来院してくれるでしょうか。これは紹介だけではなく、新患全般に言えることですが、多くの方は院に来院するまでにインターネットやSNSであなたの院を検索するでしょう。
院の外観や施術室はきれいなのか、どんな先生が施術をしてくれるのか、他の人の評価はどうなのかなど、できるだけ多くの情報を得ようと調査をします。そのとき、インターネットやSNSに院の情報がまったく出ててこないと、「本当に大丈夫かな?」と不安感を抱く可能性があります。ホームページ、検索サイト、クチコミ、SNSなどでは常に最新の情報に更新し、あなたの院に行こうか迷っている方の後押しとなるような情報を発信するように心がけましょう。
まとめ

今回は接骨院が女性患者さまの紹介数を増したいとき、抑えるべきポイントを7つご紹介しました。紹介が絶えず、女性の新患が増え続けているという接骨院は、他の接骨院と比べて、特別な施術をしているとか、珍しいサービスを導入しているというわけではありません。女性患者さまの紹介を生むために戦略的な仕掛けを仕込んでいるだけなのです。
ご紹介した7つのポイントを抑えて、紹介が紹介を生む、たくさんの方に愛される接骨院になりましょう。


 接骨院マネジメントシステム「ハニースタイル」は、効率的なネット集客と予約システム、患者とのコミュニケーション手段を提供する接骨院、整骨院、鍼灸院など柔整業界に特化したシステムです。
接骨院マネジメントシステム「ハニースタイル」は、効率的なネット集客と予約システム、患者とのコミュニケーション手段を提供する接骨院、整骨院、鍼灸院など柔整業界に特化したシステムです。
















